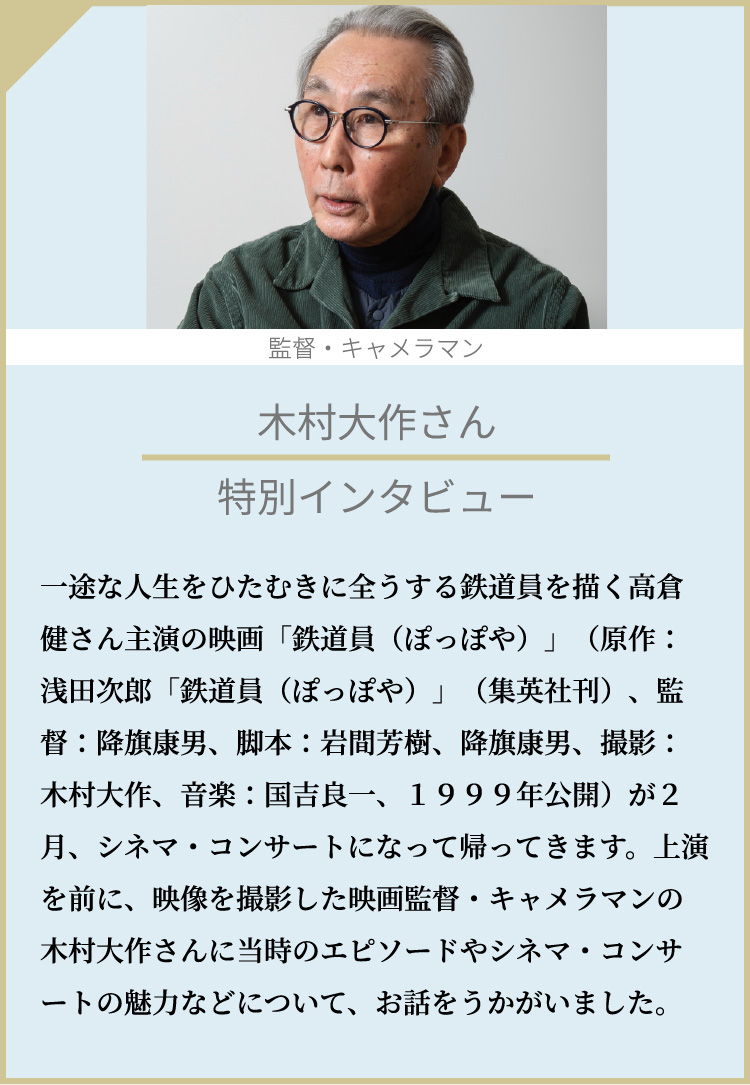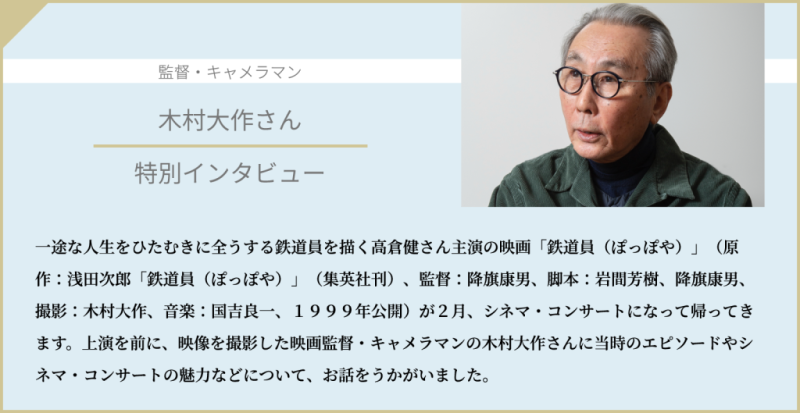「鉄道員」撮影時の心境

「強いて言えば、俺自身が、乙松同様、社会では定年退職を迎える60歳になろうかという時期の撮影だったから、ずっとやってきたものをリタイヤしなくてはならない『終末』という精神を込めて取り掛かった。オレの仕事はリタイヤしなくていいから助かったけど」と木村さん。
雪
木村さんは、健さん出演の映画を計9本撮影しました。今回の「鉄道員(ぽっぽや)」をはじめ、「八甲田山」(1977年公開)、「駅STATION」(1981年公開)、「夜叉」(1985年公開)など有名作ぞろいです。木村さんの映像には、雪の場面が多く、とりわけ吹雪のように激しい降雪が目立ちます。「氷点下10度の空気」が映り込んでいるとも言えます。
「雪を撮影する名人ともいわれるけれど、ほんと雪ばかり。雪は汚いものを全部消すからね。ドピーカンの晴天の下の雪もいいけれど、やはり降っている雪がいい。雪は1年の経過も出せるし、情緒、詩情が出る。画面に出ている俳優の心情も、人生すべてが表現できる。特に高倉健の場合、高倉健が立っていて、雪が降ればいい。そこにアクションが加われば、必ずヒットする。『鉄道員』のアクションはD51などの蒸気機関車だった。現実にヒットしたしね」
とはいえ、極寒の悪条件下での演技も撮影も並々ならぬものがあったでしょう。
「雪、波、風、雨……健さんは自分がどこに似合うのかがよく分かっている人だった。怒涛逆巻く海に臨んで雪が降っているような厳しいところに連れて行くと、『いいねえ』と言っていた。厳しい自然の中に自分が立つことで心情が出るかどうか。だから台詞は言う必要がないと思う」
「吹雪だと、俳優もこちらも厳しい。天に祈って、一生懸命に取り組もうとしていると、いい雪に巡り会える。待って撮る。待つことがいかに大事か。初雪を待って山小屋で2週間待ったこともある。待つことがあるから、いざ降った時、『最高だ』と思って撮っている。『八甲田山』なんて3年間にわたって、雪の中を走り回った。厳しさの中にこそ美しさがある。これは人間にも通じる。厳しさを越えた人間性は素晴らしいものになる。厳しさに突っ込んでいく勇気も大事だ」
高倉健という真っすぐな生き方
木村さんは乙松の姿と高倉健本人の姿がだぶる、と言います。定年後の再就職先の世話を焼こうとする友人の誘いを固辞する場面。「レールだったら曲がれるべ」と説得する友人に対して、乙松は「曲がれねえんだぁ、なっかなか、年をとっても」と吐露します。
「曲がれない、というのは健さんの生き方そのもの。で、俺もそうなんだよなあ。健さんは芝居していない。そのシーンに自分を置いた時に自然に出てくる自分の心情が表現になっていく。役に入り込んでいく役者ではなく、高倉健という自分の方に役を引っ張ってきてしまう」
「鉄道員」の中の高倉健さんは、一介のぽっぽやでありながら、いつしか戦後日本を支えた日本人男性の象徴ともなり、「神々しい造形」として迫ってきます。敗戦日本で体で覚えてきたことしかできない不器用な男、曲がれない男、体中で人生の苦しみを耐え抜いている男。それらが映像からにじみ出てきます。
「テストなし、本番一発撮りだけという人。とにかく稀有な俳優ですね」と、木村さんも太鼓判を押します。
撮影者の矜持
映画で登場する趣のある終着駅「幌舞駅」は、北海道富良野町にあるJR北海道・根室本線の「幾寅駅」を改造。実際には途中駅のため、腕木式信号機や「車両止め」を増設しました。ホームとレールが映る場面の撮影は、実際に運行している根室本線の急行が通らない1日2時間ほどに限られ、その都度、「車両止め」などを設置したり撤去したりと、大わらわだったそうです。木村さんは撮影1年前のお盆休みを使って単独でロケハンして「幾寅駅」を見つけたといいます。
「この映画にふさわしい駅を見つけないといけないと、ようやく借りられた2トントラックで、北海道を一週間探し回った。駅舎からホームに出るのに連絡階段があって、ここを人が歩いている姿を見たとき、『こんなのは見たことがない。これだ』と直感しました」
ところが、一つ気になったのが、コンクリート製の3本の電柱でした。これでは詩情が台無しです。
「『黒澤明監督なら、切れって言うなあ』と独り言みたいに、でも聞えよがしに言っていたら、北海道電力も協力してくれて、木の電柱に代えてくれたよ。撮影者はそういうこともする。現場を引っ張る責任があると思う」
木村さんにとっての「神」は黒澤明監督と高倉健さんといいます。木村さんは18歳から30歳まで、黒澤監督の5作品で撮影助手を務めてきました。「黒澤監督は、こうなりたいと思う人だった。この経験があったから今がある」と断言します。
黒澤映画「天国と地獄」で、酒匂川にかかる鉄橋の場面の撮影中、2階建て家屋の2階部分がどうしても映り込んでしまう事態になったそうです。「あれ、邪魔だね」と黒澤監督。当時、黒澤監督は「天皇」とまで言われた存在だっただけに、映画会社がかけあって、2階部分を切断し、撮影終了後に復元したことがあったそうです。
木村さんは、自らの監督作品以外は、映画のエンドロールで「撮影」とすることにこだわり、「撮影監督」という表記が「大っ嫌い」と言います。そこには「撮影」の格上げに配慮するような「撮影監督」の呼称を排し、「撮影者」に徹し、「映像の全責任は撮影する人にある」とする矜持が見えます。
「その意味では監督の言うことを聞かないカメラマンかもしれない。でも、責任を負っていると思うから自分の思う通りに、自分のやり方を通したい。ワンカットごとに『木村大作』というハンコを押し過ぎといわれたこともあるけれど」
映像の工夫
映画「鉄道員」では、厳然たる定年の現実を前にしたリアルな頑固者の場面に加え、回想や「夢か現か」という場面も少なくありません。両者を調和させる点、撮影は難しかったのではないでしょうか。
「完全なファンタジーですよ。でも僕はファンタジー風な幻想的なタッチで撮るということを一切しなかった。それと、回想シーンが多すぎるくらいだよね、あの映画は。僕は、回想は映画にはあってはいけないものではないかとすら思っているくらいなので、回想シーンがあると、ものすごく悩むんだよ。全編、リアリティのタッチで撮っているんだけど、回想シーンは、見ている方がすぐわかるように、デジタル技術で脱色したり、三色分解して一色だけ残したりして、微妙な表現をこらした」
志村けん、田中好子という、健さん以外でも今は亡き俳優たちの演技を見ることができます。志村さんが唯一出演した映画になりました。
「ダブルけんさんになったわけですが、志村さんは健さんの指名で、ものすごく忙しい中、出演してくれた。食堂での乱闘シーンなど全部、志村さん本人のアイデアで演技に臨んでいた。奈良岡朋子さんも出ていますが、健さんの好む共演者の方々は、健さんに言わせると『あの人には気がある』ということです」
降旗康男監督とは16作品でタッグを組みました。
「降旗監督は、出演する俳優たちが持ち込むそれぞれの演技のアイデアやプランをそのまま使うことができる。不思議と、そういう器量がありましたね」と振り返ります。
シネマコンサート
「鉄道員」では、要所要所で「テネシー・ワルツ」をはじめとする音楽がすーっと入ってきて、画面をつないでいきます。坂本美雨さんが歌うエンディング曲「鉄道員(TETSUDOIN)」(奥田民生作詞・坂本龍一作曲)も、透明で無機的で、凍てつくような映画の風景に溶け込んでゆくようです。映画に音楽は欠かせません。
「そう、音楽なしなんて、ありえない。俺の監督作品、「劔岳 点の記」で使う音楽は、意外かもしれないけれど、大好きなビバルディやバッハといったクラシック音楽なんだけど、とにかく音楽のない映画なんてない」
木村さんは以前、自ら撮影した映画「八甲田山」のシネマ・コンサートを観客席で見たといいます。大画面の映画と生の演奏が客席に迫ってくるコンサートスタイルに接し、興奮したといいます。
「これまでで一番感動した『八甲田山』だった。見ていた人の多くも、そう思ったでしょう。オーケストラの演奏が生々しいからね。軍隊のラッパ音の微妙な細かい表情まで再現していて感心しました」
「今度は『ぽっぽや』だからねえ。ラストで坂本美雨さんも歌うんでしょう。これがシネマ・コンサートになると聞いて、最高だと思った」と、今回の「鉄道員」のシネマ・コンサートにも大きな期待を寄せ、「いろんな映画で、シネマ・コンサートをどんどんやってほしい」と話しています。
主催: PROMAX/ディスクガレージ/BS朝日/朝日新聞社/TOKYO FM/TBSラジオ
協力: 集英社/東映/「鉄道員(ぽっぽや)」製作委員会
企画・制作